厚生労働省は「在職老齢年金制度」の基準額を引き上げ、高齢者が働きながら年金を満額受給しやすくする方針を固めた。
現行制度では、65歳以上で給与+年金の合計が月50万円を超えると、その超過分の年金が減額される仕組みだが、2026年4月からは基準額を62万円に引き上げる。これにより、月収と年金の合計が62万円未満なら減額されない。対象となるのは、給与と年金の合計が50万円を超える高所得の高齢者であり、新たに約20万人が満額受給可能になると見込まれている。

年金の平均受給額が約20万円であるため、現行制度では、月に30万円以上の収入がある人が減額の対象となっていた。また、世帯単位の平均的な消費額は月30万円程度とされており、給与と年金を合わせて50万円以上の収入がある人は、老後の生活は十分に成り立つ計算になる。つまり、今回の年金改革は「65歳を過ぎても30万円以上稼げる人(=余裕で貯蓄ができる人)」に向けた改正であり、本当に必要なのかという疑問が生じる。
日本の公的年金の支出は年間50兆円に達し、国家予算の一般会計の約120兆円と比べてもその規模の大きさがわかる。50兆円のうち、約10兆円は一般会計からの支出で、残りの40兆円は特別会計から賄われている。特別会計の財源は、現役世代が支払う社会保障料が大部分を占めるが、日本は少子高齢化が進行しており、年金の支出が増え続ける一方で、それを支える現役世代の負担はますます重くなっている。このままでは、現役世代の負担が限界を迎え、持続可能性が失われるのは時間の問題だ。
現役世代の負担を軽減するには、年金の支出を抑えるか、負担を広く分散させる仕組みを構築する必要がある。そのためには、年金支出の抑制策として、現役世代の社会保障料を引き下げ、一般会計からの負担を増やす方向が望ましい。だが、最も効果的なのは年金世代の支出そのものを減らすことにある。しかし、年金受給世代の選挙権は現役世代と同じく平等にあり、受給者層が大反発すれば、どの政党も選挙に勝てなくなるため、政治的に年金の削減策は実施が難しいのが現状だ。
こうした状況の中で行われる今回の変更は、働いている高所得の高齢者に対して、年金の支出を抑えるどころか、むしろ満額支給を認めるという方向へ進んでいる。これは、長く働くことを促し、税収を増やし、健康維持を促進する狙いがあるのかもしれない。しかし、本当にこの改正が必要なのか、疑問が残る。本来の改革が必要なのは、一律の年金支給の減額だ。その痛みを国民全体で共有しなければならない。
老人の平均的な支出は月30万円とされている。それにもかかわらず、60万円以上の収入がある人に対しても年金を満額支給するのは、過剰な公平ではないか。同世代内での公平性を追求するのではなく、より若い世代を含めた社会全体の公平性を考慮するべきだ。年金改革の本質は、いかにして支出を減らすかにある。究極的には、年金制度は生活保護へと収斂していく可能性すらある。多くの人が死ぬまで働くか、自らの資産を切り崩しながら生きていくしかない時代が来るだろう。それが不可能な人々は、最低限の文化的な生活を送るための生活保護に頼るしかなくなる。
現在の日本は、かつての経済大国ではなく、世界の大富豪たちにとっては「キュートな存在」に過ぎない。国の力は衰えつつあり、かつてのように国が国民を支える体力は残されていない。したがって、多くの国民は国に頼るのではなく、自らの力で生き抜く覚悟が必要だ。国に依存すれば、国とともに沈むだけである。高齢者の負担を現役世代に押しつける仕組みは、いずれ立ち行かなくなる。これからの日本社会では、老後の負担を誰かが肩代わりしてくれる世界は消滅しつつあるのだ。
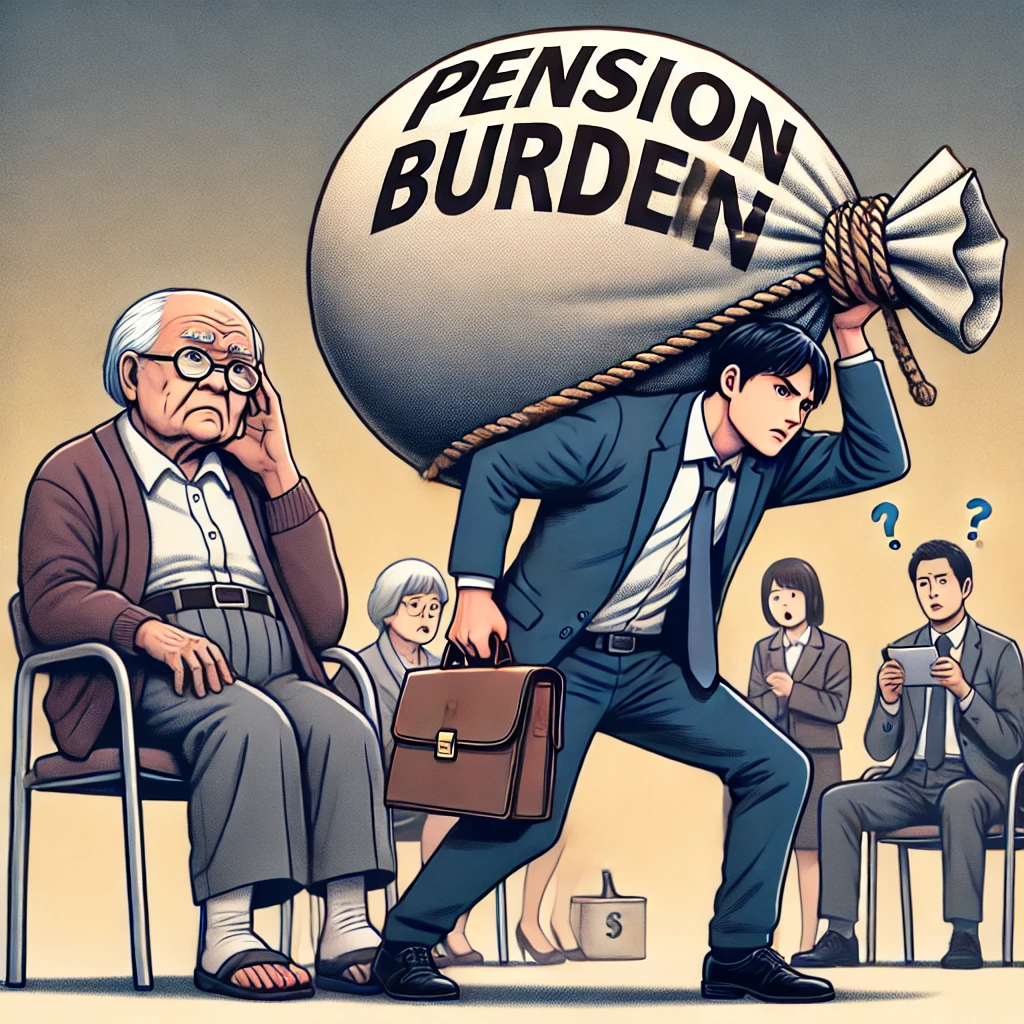


コメント