贈与は、実は相続税に加算されるケースが有る。これは、贈与をしたものが死亡したときから数えて、数年前までに行った贈与は、相続税の対象となるのだ。
以前は、3年だったが、法律が変わったので、今後は段階的に7年になっていく。
贈与加算の正しいルール(令和6年改正)
1. 基本ルール(改正前)
- 相続開始前 3年以内の暦年課税の贈与 → 相続財産に加算。
2. 改正後(2024年1月1日以降の贈与から適用)
- 相続開始が 2026年(令和8年)まで → 従来どおり 3年以内。
- 相続開始が 2027年(令和9年)〜2030年(令和12年) →
2024年1月1日以降の贈与~死亡日まで が加算対象。
→ 結果として、2027年は約3年分、2029年は約5年分…と対象期間が少しずつ延びる。 - 相続開始が 2031年(令和13年)以降 → 死亡前7年以内の贈与すべてが加算対象。
控除のルール
- 「死亡前3年を超える部分」については、合計100万円までは加算不要
👉 つまり、4年目以降〜7年目の贈与については100万円まで相続財産に含めなくてよい。
⚠️ 基礎控除110万円(暦年課税の非課税枠)とは別物
- 110万円 → 毎年の贈与で贈与税がかからない枠。
- 100万円 → 「3年を超える加算部分」について相続財産に含めなくてもよい枠。
まとめ表
| 相続開始年 | 加算対象期間 | 特例 |
|---|---|---|
| 2026年まで | 死亡前3年以内 | – |
| 2027年 | 2024/1/1〜死亡日 | 3年超部分に100万円控除 |
| 2028年 | 2024/1/1〜死亡日 | 同上 |
| 2029年 | 2024/1/1〜死亡日 | 同上 |
| 2030年 | 2024/1/1〜死亡日 | 同上 |
| 2031年以降 | 死亡前7年以内 | 同上 |
具体的な数字を考えたい。配偶者に2025年から年間300万円の贈与を指定と仮定する。定額贈与ではなく、通常の贈与として、贈与のたびに契約書を交わすと仮定する。これが5年継続した際には、どの時点まで贈与を与えた側は生きなくてはいけないだろうか?
状況としては、2025年から2029年に毎年300万円贈与となったので、最終的に贈与した年は2029年となる。ここから7年は生きなくてはいけない。つまり、2036年末より長く生き延びれば、これらの贈与は相続税の対象外となるのだ。
どうだろうか?。かなり長く考えなくてはいけないのだ。
しかし、ながら相手が配偶者の場合には、。。。。である。また、子供であれば、相続時精算贈与の検討をすればいい。
以下では、配偶者に300万円の贈与を5年間してから、すぐに死んだ場合のシミュレーションを実施した。他の仮定としては、被相続人は5000万円の現金をもっており、相続人は配偶者と子供1人と仮定する。
💡 前提条件
- 生前贈与:2025~2029年に配偶者へ毎年300万円(合計1,500万円)。
→ 贈与税合計:45万円(毎年9万円)。 - 死亡時(2030年想定)の現金:5,000万円。
- 相続人:配偶者+子供1人(2人)。
- 遺産分割:法定相続分どおり(配偶者1/2=3,250万円、子1/2=3,250万円)。
- 配偶者控除(1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税)あり。
1. 相続財産の合計
- 現金:5,000万円
- 贈与加算:1,500万円
- 合計 6,500万円
2. 相続税の総額(国税庁方式)
- 基礎控除:3,000万円 + 600万 × 2人 = 4,200万円
- 課税価格:6,500万 − 4,200万 = 2,300万円
👉 まず「法定相続分」で分けて課税価格を割り振る。
- 配偶者:2,300万 × 1/2 = 1,150万円
- 子:2,300万 × 1/2 = 1,150万円
3. 相続税の速算
- 課税価格1,150万円 → 税率15%、控除50万円
- 1,150万 × 15% − 50万 = 122.5万円
👉 相続税総額:245万円
4. 相続税の配分
- 本来の按分:配偶者122.5万円、子122.5万円。
- ただし、配偶者控除により配偶者の税額はゼロ(1億6千万円まで非課税)。
- その分の税は子にしわ寄せされるのではなく、単純に免除。
👉 実際の負担は子のみ:相続税122.5万円
5. 贈与税額控除
- 配偶者が過去に支払った贈与税:45万円。
- 配偶者は相続税がゼロ → 控除の適用先がない。
- したがって 贈与税は戻ってこない(損になる)。
✅ 結論(配偶者+子1人、法定相続分の場合)
- 生前贈与税:45万円(戻らない)
- 相続税:子が 122.5万円 負担、配偶者はゼロ
- トータル負担=167.5万円
💡 ポイント
- 贈与しなかった場合でも、配偶者控除があるので配偶者の相続税はゼロ。
- 贈与した場合、贈与税(45万円)が余計にかかってしまい、かえって不利。
一方で、最後の贈与をしたあとの10年後に死亡した場合、つまり贈与が相続税の対象にならないケースを考える。
はい、条件を「最後の贈与(2029年)から10年後に死亡(=2039年)」に変えて計算してみます。
💡 前提条件
- 贈与:2025〜2029年に配偶者へ毎年300万円(合計1,500万円)。
- 贈与税:毎年9万円 → 5年間で45万円(暦年課税・一般贈与)。
- 死亡時点(2039年)の財産:現金5,000万円。
- 相続人:配偶者+子1人。
- 遺産分割:法定相続分(配偶者1/2、子1/2)。
- 相続税の計算:死亡前7年を超えている贈与は相続財産に加算されない。
1. 相続財産の課税価格
- 現金:5,000万円
- 生前贈与加算:なし(7年を超えているため対象外)
- 相続財産合計:5,000万円
2. 相続税の総額(国税庁方式)
- 基礎控除:3,000万+600万×2人=4,200万円
- 課税価格:5,000万 − 4,200万 = 800万円
法定相続分で按分
- 配偶者:400万円
- 子:400万円
相続税計算
- 400万 → 税率10%、控除0
- 税額:400万 × 10% = 40万円
👉 相続税総額:80万円
3. 配偶者控除適用
- 配偶者の税額40万円 → 配偶者控除でゼロ。
- 実際の負担:子が 40万円。
4. 贈与税額控除
- 生前に支払った贈与税:45万円(2025〜2029年分)。
- しかし、死亡時点で贈与は相続税に加算されないため、相続税から控除できない。
- よって 45万円は戻ってこない。
✅ 結果(2039年に死亡した場合)
- 贈与税(過去):45万円
- 相続税(子のみ負担):40万円
- 合計負担:85万円
📌 比較
- 2030年に死亡した場合 → トータル負担 167.5万円
- 2039年に死亡した場合 → トータル負担 85万円
👉 7年を超えて生きた場合、贈与は相続に加算されないので、相続税がぐっと減る。
👉 ただし、過去に払った贈与税45万円は戻らないため、やはり「配偶者への贈与」は税務的には損になることが多い。
条件をそろえて「贈与あり(配偶者に毎年300万円×5年)」と「贈与なし」を、
- すぐに死亡(2030年、最後の贈与直後)
- 10年後に死亡(2039年)
の2パターンで比較表にした。
贈与あり vs 贈与なし(配偶者+子1人、法定相続分)
| 区分 | 贈与あり(2030年死亡) | 贈与なし(2030年死亡) | 贈与あり(2039年死亡) | 贈与なし(2039年死亡) |
|---|---|---|---|---|
| 贈与額 | 配偶者に合計1,500万(2025〜29年) | なし | 同左 | なし |
| 贈与税(生前) | 45万円 | なし | 45万円 | なし |
| 死亡時財産 | 5,000万円 | 6,500万円(贈与してない分も残る) | 5,000万円 | 6,500万円 |
| 相続財産への加算 | 1,500万円(3年以内) | – | なし(7年以上経過) | – |
| 課税価格 | 6,500万 − 4,200万=2,300万円 | 同じ2,300万円 | 5,000万 − 4,200万=800万円 | 6,500万 − 4,200万=2,300万円 |
| 相続税総額 | 245万円 | 245万円 | 80万円 | 245万円 |
| 配偶者控除後の実負担 | 配偶者0、子122.5万 → 贈与税控除できず → 167.5万円(=122.5+45) | 配偶者0、子122.5万 → 122.5万円 | 配偶者0、子40万 → 贈与税控除できず → 85万円(=40+45) | 配偶者0、子122.5万 → 122.5万円 |
| 最終負担 | 167.5万円 | 122.5万円 | 85万円 | 122.5万円 |
| 比較効果 | 贈与した方が 45万円損 | – | 贈与した方が 37.5万円得 | – |
✅ 結論
- すぐに死亡(2030年) → 贈与した分が持ち戻され、しかも配偶者には控除があるため、贈与税が無駄になる。
→ 贈与した方が 45万円損。 - 10年後に死亡(2039年) → 贈与は持ち戻されず、相続税が軽減される。
→ 贈与した方が 37.5万円得。
💡つまり、「長生きできる前提なら贈与の節税効果がある」が、「早く亡くなると逆効果になる」ということになる。
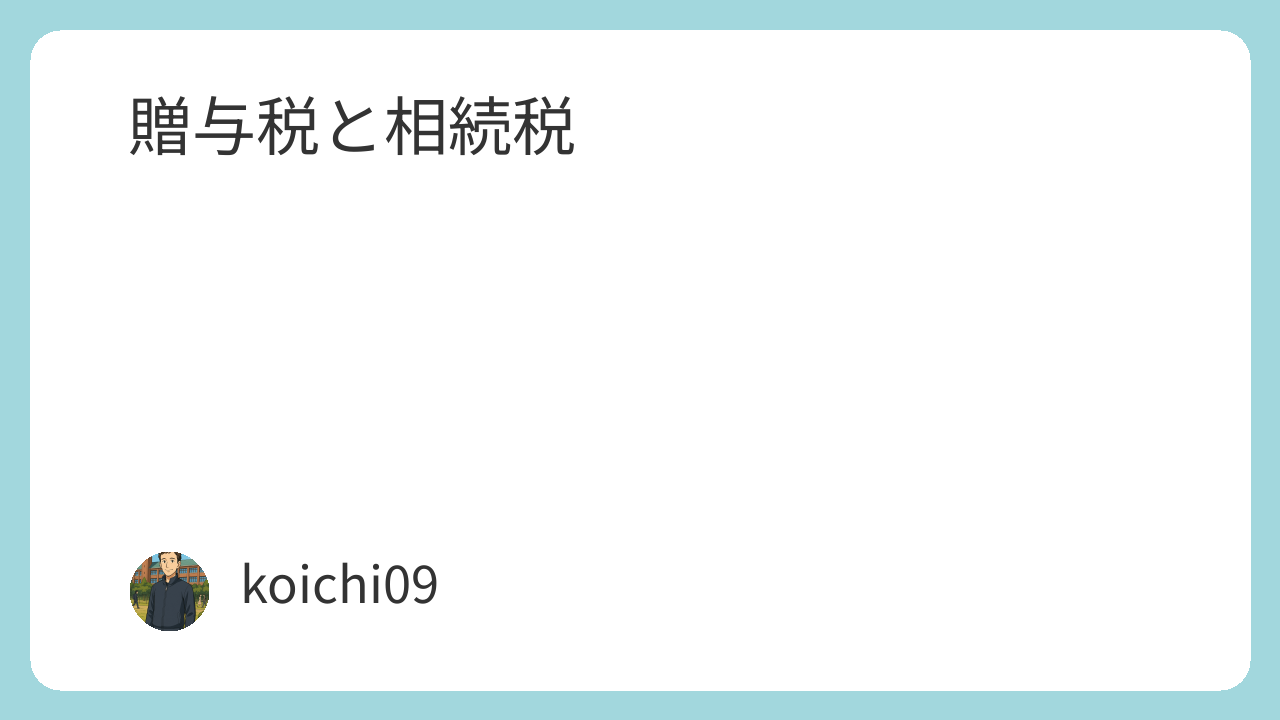
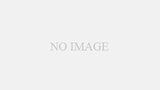
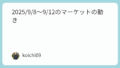
コメント