高配当株に興味があるが、なかなか手が出ない。金利が上昇する局面では、高配当株の価格が下がるのではと思うのと、相対的な魅力が下がるのではと考えているからだ。
そこで、高配当株と金利の関係を紹介しているサイトを探していたところ、以下のサイトが優秀だったので紹介したい。

以下は上記のリンクの簡単なまとめだ。詳細は上記のリンクを見てほしい。
結論としては、増配重視、企業業績安定成長の株は金利の変動に対する感応度が低かった。金利の影響は大きいものだが、それ以上に成長する企業を見つけて投資をするという原則には何も変わりがないのだと思われる。
配当の魅力
配当には多くの魅力がある。自分が保有する企業から定期的に配当金を受け取ることは、その企業の経営規律・健全性・将来への自信を示す証拠でもある。
しかし、安定したキャッシュフローを持つ企業の株価は、金利変動に対してより敏感に反応する傾向がある。ここでは、その関係を詳しく分析し、投資家がどの程度気にすべきかを検討する。
資産価格と金利 ― シーソーの関係
金利と資産価格は、シーソーの両端に乗った幼稚園児のような関係にある。金利が上がると資産価格は下がり、金利が下がると資産価格は上がる。
この動きは、予測可能なキャッシュフローを生む長期資産(長期債など)で特に顕著だ。
配当株も債券ほど安定はしないが、同様の関係を示す。過去のデータを見ると、金利上昇期には高配当株が無配株や低配当株に劣後する傾向がある。逆に金利低下期には、高配当株が優位に立つ。
筆者は1953年からの米10年国債利回りの月次変化を分析し、上昇期・安定期・下落期での配当株のパフォーマンスを比較した。
結果、金利上昇・下落期には高配当株と低配当株の差が大きいが、金利が安定している期間ではその差は縮まった。長期的に見ると、両者のパフォーマンス差はさらに小さい。
📊 Exhibit 1:金利と配当株のパフォーマンス関係
テーマ:10年国債利回りの変化と、配当利回り別の株式リターン
| 金利環境 | 高配当株 | 低配当株/無配株 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 金利上昇期 | ⬇️パフォーマンス悪化 | ⬆️比較的堅調 | 高配当株は債券的性格が強く金利上昇に弱い |
| 金利安定期 | ↔️差が縮小 | ↔️差が縮小 | 双方の差は限定的 |
| 金利低下期 | ⬆️パフォーマンス上昇 | ⬇️やや劣後 | 高配当株は金利低下の恩恵を受けやすい |
金利感応度の測定
次に、配当利回り別ポートフォリオのリターン感応度を分析。
市場全体および10年国債利回りの月次変化に対する感応度を計測した。
正の値は同方向に動く関係、負の値は逆方向の関係を示す。
結果として、債券的な性質を持つ(定期的にキャッシュを生む)企業群は、株式市場のリスク感応度が低いことがわかった。
これらの企業は成熟しており、景気循環に影響されにくい。そのため、長期的に安定配当を維持・増配できる傾向がある。
一方、こうした高配当株は、金利上昇時にマイナスの影響を受けやすい。
なぜなら、景気拡大期に成長によるプラス要因が少なく、上昇する金利の悪影響を打ち消せないためだ。逆に、金利が下がると恩恵を受けやすい。
📈 Exhibit 2:市場感応度と金利感応度
テーマ:配当利回り別ポートフォリオのリスク特性
| 配当利回り | 市場感応度(β) | 金利感応度 | 解釈 |
|---|---|---|---|
| 高配当株 | 低い(安定) | 負(上昇時に下落) | 成熟企業・景気非連動型 |
| 低配当株 | 高い(変動大) | 正または中立 | 成長企業・景気連動型 |
規模別の傾向
配当利回りと金利感応度の関係をより深く理解するため、時価総額別にも分析を行った。
成熟度の指標としての時価総額を見ると、SPY(大型株)、MDY(中型株)、SLY(小型株)の順に、金利感応度が高まる傾向が見られた。
大型株は成熟・資本力・収益源の多様性があり、一般的に市場や金利変化に対して安定している。
🏢 Exhibit 3:時価総額別の金利感応度(SPY / MDY / SLY 比較)
| 区分 | 代表ETF | 特徴 | 金利感応度 |
|---|---|---|---|
| 大型株 | SPY | 成熟・資本力・多様な収益源 | 低い(安定) |
| 中型株 | MDY | 成長と安定の中間 | 中程度 |
| 小型株 | SLY | 景気変動の影響大 | 高い(不安定) |
📘 まとめ
- 大型株ほど「金利変化に強く、市場にも安定的」。
- 小型株は景気循環に左右されやすく、金利上昇局面で特に弱い。
業種別の傾向
さらに12業種ポートフォリオを分析したところ、防御的性質を持つ業種(公益、生活必需品など)は、金利上昇時に悪影響を受けやすいことが分かった。
これらの業種はキャッシュフローが安定しているため、金利上昇で魅力が薄れる。
一方、景気循環型の業種(エネルギー、耐久消費財など)は逆に、金利上昇時に好調となる傾向がある。
🏭 Exhibit 4:業種別の金利影響(12業種分析)
| 業種タイプ | 代表業種 | 金利上昇時 | 金利低下時 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 防御的(ディフェンシブ) | 公益、生活必需品 | マイナス影響(⬇️) | プラス影響(⬆️) | キャッシュフロー安定だが金利上昇に弱い |
| 景気循環型 | エネルギー、耐久消費財 | プラス影響(⬆️) | マイナス影響(⬇️) | 景気好調期=金利上昇時に強い |
💡 理解のポイント
- 金利上昇は「成長・景気好調のサイン」でもある。
- そのためエネルギー・工業などが好調になりやすく、
一方で公益・生活必需品などの「防御株」は魅力が相対的に低下。
注目ファンドの分析
最後に、配当重視型のETFのうち、モーニングスターが高評価を付ける銘柄(10年以上の実績を持つ7ファンド)を分析。
金利感応度が最も低かったのは Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG) で、市場感応度は高いが、金利には比較的鈍感だった。
一方で、最も金利感応度が高かったのは Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)。
同ETFは「高配当利回り指数(FTSE High Dividend Yield Index)」を追跡しており、高配当株を重視する設計のため、金利変動の影響を受けやすい。
💼 Exhibit 5:代表的な配当ETFの金利感応度ランキング
| ETF名 | ティッカー | 特徴 | 金利感応度 |
|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 増配重視・安定成長 | 低(安定) |
| iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO | 成長+安定バランス | 中程度 |
| SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 高配当+安定企業 | 中〜高 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 利回り重視・大型株中心 | 高(敏感) |
📊 結果の要点
- VIG は金利変化に最も鈍感(堅実)
- VYM は配当利回り重視のため、金利上昇に弱く下落しやすい
- 増配重視のファンドの方が長期的な安定性に優れる
結論:金利変動を恐れるな
配当株や配当ETFが金利変動にどう反応するかを理解することは有益だ。
しかし、その知識を「行動」に直結させる必要はない。
金利は上がったり下がったりするものであり、タイミングや幅を正確に予測できる人はいない。
質の高い企業に投資し、継続的に株主へ還元することこそ、あらゆる金利環境下で有効な戦略である。
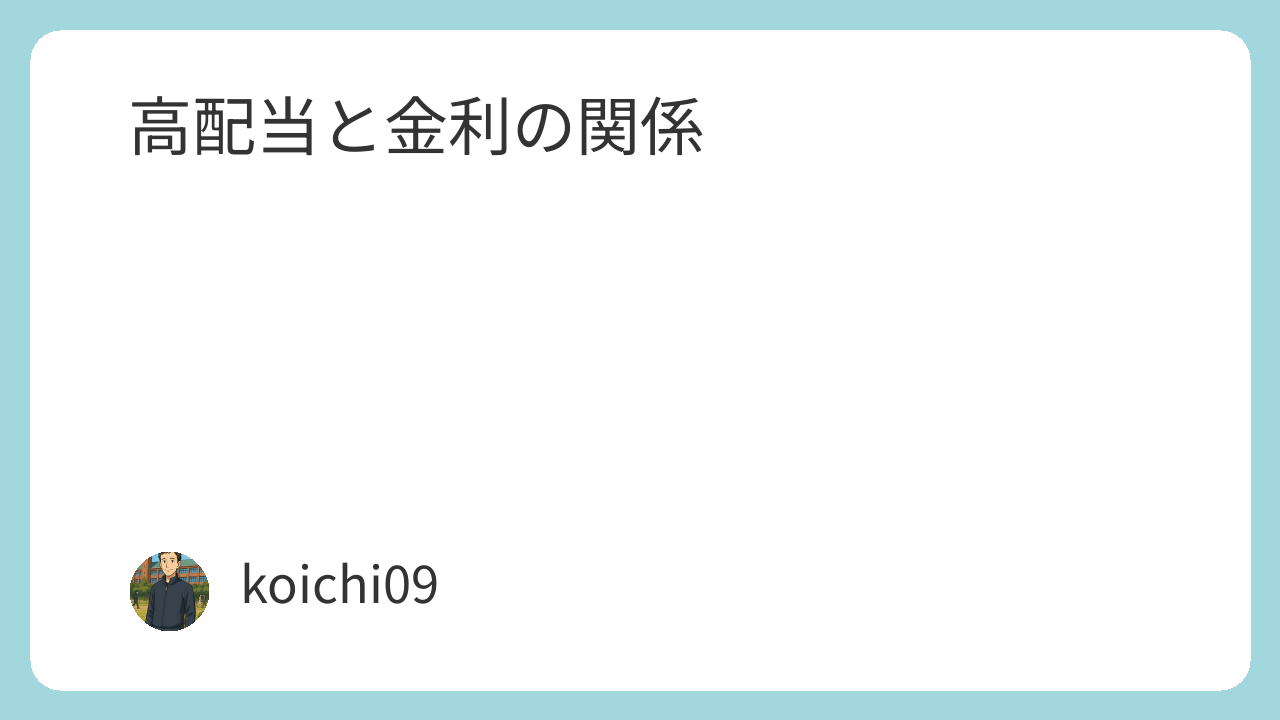
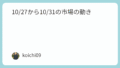
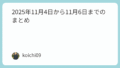
コメント