譲渡所得の計算について
土地や建物を売却した際の譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入時の手数料)および譲渡費用を差し引いて計算する。取得に要した実額が不明である場合や、実際の取得費が売却価格の5%を下回る場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費として計算することが認められている。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、購入時に支払った代金や仲介手数料、登記費用などが含まれる。譲渡費用には、売却時の仲介手数料、測量費用、解体費用などが該当する。
取得費が不明な場合の取扱い
取得費(購入時の代金や手数料など)が不明、または実際の取得費が売却価格の5%未満の場合、売却価格の5%を取得費として計算することが認められている。この方法を概算取得費と呼ぶ。
具体例
ケース1:取得費が明確な場合。 例えば、購入価格が1,000万円、譲渡費用(仲介手数料など)が100万円、売却価格が2,000万円だった場合、取得費は1,000万円となる。この場合の譲渡所得は、売却価格2,000万円から取得費1,000万円と譲渡費用100万円を差し引いた900万円となる。
購入価格:1,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):100万円
売却価格:2,000万円
この場合の譲渡所得:
2,000万円-(1,000万円+100万円)=900万円
ケース2:取得費が不明な場合。 例えば、売却価格が2,000万円、譲渡費用が100万円であり、取得費が不明である場合、概算取得費として売却価格の5%(2,000万円 × 5% = 100万円)を適用する。この場合の譲渡所得は、売却価格2,000万円から概算取得費100万円と譲渡費用100万円を差し引いた1,800万円となる。
売却価格:2,000万円
譲渡費用:100万円
取得費不明 → 概算取得費(2,000万円 × 5%)= 100万円
この場合の譲渡所得:
2,000万円-(100万円+100万円)=1,800万円
取得費が分からないと、課税対象となる譲渡所得が大きくなり、結果として税負担が増加する。そのため、できる限り購入時の契約書や領収書を保管しておくことが重要となる。
なぜ5%なのか?
この5%ルールは、税務上の便宜的な基準であり、特に古い物件では取得時の資料が残っていないことが多いため、納税者に極端な不利益を与えないために設けられている。
歴史的に見ても、土地や建物の価値は長期的に上昇する傾向がある。そのため、取得費をあまりに低く見積もると、課税額が大きくなりすぎる可能性がある。こうした背景から、国税庁は「取得費不明時の最低限の基準」として、売却価格の5%を取得費として認めることとした。
ただし、実際には取得費が5%を超えることがほとんどであるため、可能な限り取得費の証拠を残しておくことが望ましい。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)
譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超える居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、以下の軽減税率が適用される。
| 課税対象額 | 適用税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21%(所得税10% + 復興特別所得税0.21% + 住民税4%) |
| 6,000万円超の部分 | 20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%) |
通常、5年を超えて所有した土地や建物を売却した場合、長期譲渡所得として分離課税される。その税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)であるが、軽減税率を適用すると所得税5%分、住民税1%分が軽減される。
軽減税率の適用条件
この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある。
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年以上であること
- 売却する不動産が、自己の居住用財産(マイホーム)であること
- 過去にこの軽減税率の適用を受けていないこと
ひとり親控除について
ひとり親控除は、現に婚姻していない人が一定の子を扶養している場合に、35万円の所得控除を受けられる制度である。適用を受けるためには、以下の3つの条件すべてを満たす必要がある。
| 適用条件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 生計を一にする子がいること | 子の年齢に関係なく、納税者と同居し生計を共にしていることが条件となる。 |
| 2. 子の総所得金額が48万円以下であること | ここでいう所得とは、給与所得控除後の金額を指し、アルバイトなどの収入が48万円を超える場合は適用外となる。 |
| 3. 納税者の合計所得金額が500万円以下であること | 500万円を超える所得がある場合、この控除は適用されない。 |
ひとり親控除の背景
これまで、離別・死別した単身者には「寡婦控除」や「寡夫控除」という所得控除が設けられていたが、未婚の父母には適用されていなかった。シングルファザーやシングルマザーの生活の厳しさが社会問題となる中、税制面から支援する目的で、2020年に寡婦控除・寡夫控除を改組し、ひとり親控除が創設された。
この制度によって、未婚のひとり親も所得控除を受けられるようになり、税負担の軽減が図られるようになった。

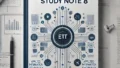

コメント