JEPIと米国高配当ETF(VYM・HDV・SPYD)の比較
投資の基本は、全世界株式インデックス(オルカン)であることに疑いの余地はない。国際分散投資を徹底でき、リスクとリターンのバランスが最適化されているため、初心者から上級者まで王道の選択肢と言える。特に日本の個人投資家には、これ一本で世界経済全体の成長を取り込めるという安心感が大きな魅力だ。
一方で、米国市場への信頼が厚い人々も多く存在する。そうした投資家にとっては、S&P500を投資対象とするインデックスも十分に合理的な選択肢だ。米国は世界経済を牽引する存在であり、長期的に見ればS&P500単独でも高い成長性を示してきたことが知られている。
ただし、インデックス投資の宿命として、価格のボラティリティ(変動幅)は無視できない要素となる。市場全体の動きに連動するため、急落時や大きな調整局面では大きな含み損を抱えることもある。特に「取り崩し期」つまり資産を売却して生活資金として使うタイミングでは、自分が想定していた価格で売却できないリスクが現実問題として生じる。あなたもすでに感じているかもしれないが、資産運用の出口戦略においては、こうした価格変動リスクは無視できない。
この点において、高配当株投資は極めて実用的な選択肢になり得る。インカムゲイン(配当金)がメインの収益源となるため、株式を売却しなくても現金収入が得られるのが最大のメリットだ。生活費の足しにしたり、計画的に再投資することで、複利効果も得られる。
高配当株のリスクとしては、単一銘柄に依存すると業績悪化などで減配・無配のリスクがあるが、これは複数の銘柄に分散投資することで大幅に緩和できる。銘柄分散がきちんとなされていれば、個別の株価変動は相殺され、全体としては価格変動がマイルドになる傾向がある。配当についても、ある程度の安定性が見込めるため、キャッシュフロー目的の投資には非常に使いやすい。
このように、インデックス投資と高配当株投資はどちらが優れているかではなく、目的やライフステージに応じて使い分けるべきものだと考えるべきだろう。積立期にはオルカンやS&P500で資産の最大化を目指し、引退後や資産取り崩し期には高配当株で現金収入を得る、というハイブリッドな戦略も十分に理にかなっている。
今回は、以前から気になっていた高配当投資の一角であるJEPIについて詳細を調べることにした。JEPIは表面的には高い分配金を提供することから「高配当株」のカテゴリーに含められることが多いが、実態はそのイメージとは異なる。
正確には、JEPIは高配当株そのものではなく、S&P500を中心とした株式ポートフォリオを保有しながら、同時にカバードコール戦略を用いるETFである。つまり、保有株に対してコールオプションを売却することでオプション・プレミアムを獲得し、それを分配金として投資家に還元する仕組みになっている。オプションの売却益がメインのインカム源となるため、純粋な企業の配当金とは異なる性質を持つ。高配当株ETFとは違い、オプション市場の状況やボラティリティによって分配金の水準が変動しやすいことも特徴の一つだ。
高配当株の分析やその戦略的な使い方については、すでに多くの書籍や専門誌が取り上げており、基礎知識として浸透している。特に日本でも人気のあるVYMやHDVなど、いわゆる「高配当株ETF」の分析記事や書籍は豊富だ。
そのため、今回はあえてJEPIにフォーカスを当て、そのパフォーマンスがどのようなものか、他の高配当ETFと比べてどのような特徴を持つのかを掘り下げてみた。
1. 年間配当利回り(最新値・平均値)
| ETF名 | 最新利回り | 過去の平均利回り | コメント |
|---|---|---|---|
| JEPI (JP Morgan Equity Premium Income ETF) | 約7.5%(直近12か月) | 2021年7.46%、 2022年10.07%、 2023年 8.48%、2024年7.67% | 毎月分配型のカバードコールETF。高いインカム収入が特徴だが、分配金は市況次第で変動が大きい。 |
| VYM (Vanguard 高配当株式ETF) | 約3.0%(3.689ドル ÷ 125.24ドル) | 約3.1~3.2% | 大型・中型株に幅広く分散投資。高配当ETFの中では利回り低めだが、安定志向で値上がり益も狙える。 |
| HDV (iShares コア 米国高配当株ETF) | 約3.5%(4.0746ドル ÷ 115.18ドル) | 約3.7%前後 | 財務健全性の高い高配当株中心で、比較的安定的な分配。 |
| SPYD (SPDR S&P500高配当株ETF) | 約4.5%(1.9097ドル ÷ 42.02ドル) | 約4.6%程度 | S&P500構成銘柄のうち高配当80社に均等投資。REIT含むため利回りは高いが、株価成長はやや低め。 |
- JEPI (JP Morgan Equity Premium Income ETF)
- 最新利回り:約7.5%(直近12か月合計ベース)。
- 毎月分配型のカバードコールETFであり分配金額の変動が大きいですが、過去の平均利回りはおおむね7~8%台を推移している
- VYM (Vanguard 高配当株式ETF)
- 最新利回り:約3.0%(直近1年の分配金合計3.689ドル、株価125.24ドルに基づく)。
- 平均利回りは約3.1~3.2%**程度で、高配当ETFの中では低め
- その分、構成銘柄数が多く分散が効いた安定志向のETF
- HDV (iShares コア 米国高配当株ETF)
- 最新利回り:約3.5%(直近1年分配金合計4.0746ドル、株価115.18ドル)。
- 平均利回りは約3.7%前後で、VYMより高くSPYDより低い水準
- 大型株かつ財務健全な高配当株に絞った指数に連動するため利回りはそこそこ高く、分配も比較的安定している。
- SPYD (SPDR ポートフォリオ S&P500高配当株式ETF)
- 最新利回り:約4.5%(直近1年分配金合計1.9097ドル、株価42.02ドル)。
- 平均利回りは約4.6%程度と、今回比較中では最も高い利回り水準。
- S&P500構成銘柄のうち高配当上位80社に均等投資するETFで、不動産(REIT)含む高利回り銘柄を多く組み入れるため利回りは高いですが、その分後述の資産価値(株価)の伸びは抑えられている。
※上記利回りはすべて**税引前(グロス)**の分配利回り
2. 株価リターン(値上がり益:配当除き)
| ETF名 | 株価上昇率(期間) | 年率換算 | コメント |
|---|---|---|---|
| JEPI (JP Morgan Equity Premium Income ETF) | 設定来:ほぼ横ばい(2020年5月~) | +1%未満 | S&P500採用銘柄+カバードコール戦略で構成。インカム重視のためキャピタルゲインは限定的。 |
| VYM (Vanguard 高配当株式ETF) | 過去10年:+82% | 約+6% | 広く分散された構成で市場平均に近い動き。高配当ながら株価成長も期待できる。 |
| HDV (iShares コア 米国高配当株ETF) | 過去10年:+50%前後 | 約+4% | ディフェンシブ高配当株が中心で、値動きは安定的。大きなキャピタルゲインは見込みづらい。 |
| SPYD (SPDR S&P500高配当株ETF) | 設定来(2015年~):+34%過去5年:+7% | 約+3~4%(設定来)約+1%強(5年) | 高配当だが景気敏感株が多く、株価成長は鈍い。コロナ後の回復もやや遅れた。 |
- JEPI
- 指数(株価)のリターンはごくわずか
- S&P500採用銘柄で構成しつつオプションプレミアム収入を得る戦略のため、大きな値上がり益は狙いにくく、設定来の株価は概ね横ばい(年率換算で+1%未満)にとどまる。
- 例えば2020年5月の設定時から直近まで基準価額は50ドル台半ばで推移しており、キャピタルゲイン(値上がり益)はほぼゼロでした。その分、高いインカムゲイン(利回り)を投資家に提供している。
- VYM
- 株価の長期上昇率は比較的良好です。
- 他の高配当ETFに比べ広く分散された構成のため、市場平均に近い値動きとなり、過去10年間の株価上昇率は+82%(年率換算約6%)に達している。
- 高配当株中心ながら一定の値上がり益も狙える点が特徴で、トータルリターンでは後述の通りHDVやSPYDを上回っている。
- HDV
- 株価上昇率は中程度。
- エネルギーや生活必需品などディフェンシブ高配当株が多く含まれる影響もあり、過去10年の株価上昇率は+50%前後(年率約4%)にとどまる。
- 値動きの安定性と引き換えに、大きなキャピタルゲインは期待しづらいETFです。
- ただし2022年のような下落局面ではS&P500を大きく上回る耐性を見せた。
- SPYD
- 株価の成長は鈍く低迷傾向
- 高利回り銘柄に均等投資するため、景気敏感セクターの影響を受けやすく、特にコロナ禍で大きく下落した後の回復が遅れました。設定(2015年)以来の株価上昇率はわずか+34%程度で年率換算約3~4%にとどまります(過去5年では+7%と年率1%強)。
- このため値上がり益という観点では4つの中で最も劣後しています。
3. トータルリターン(配当込み)参考値
各ETFのリターンを以下にまとめてみた。
| ETF名 | トータルリターン (年率) | キャピタルゲイン(年率) | 配当利回り(年率平均) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| JEPI (JP Morgan Equity Premium Income ETF) | 約+9~10% (設定来) | 約+0~1% | 約7~8% | 高いインカム収入(オプション+配当)がメイン。株価上昇は限定的で、トータルは分配金で稼ぐタイプ。 |
| VYM (Vanguard 高配当株式ETF) | 約+8~9% (過去10年) | 約+6% | 約3% | 高配当と株価成長をバランス良く狙える。安定志向でトータルリターンも優秀。 |
| HDV (iShares コア 米国高配当株ETF) | 約+6~7% (過去10年) | 約+4% | 約3.5~4% | ディフェンシブな構成で値動き安定。インカムもそこそこ高いが、成長性は中程度。 |
| SPYD (SPDR S&P500高配当株ETF) | 約+5~6%(設定来)約+4%(過去5年) | 約+3~4%(設定来)約+1%強(5年) | 約4.5~5% | 高配当重視でインカムは高いが、株価成長は鈍い。景気敏感株が多く値動きも不安定。 |
各ETFのトータルリターン(配当再投資込みの総合リターン)を比較すると、VYMとJEPIが比較的高水準となっています。例えばVYMは設定来トータルリターン年率+8.1%に達し、同期間のS&P500(約+10%)には及ばないもののHDVやSPYDを上回ります。一方HDVやSPYDの年率リターンはおおよそ5~7%程度と推定され、SPYDは高利回りゆえの低成長が響き最も低調となる。
JEPIのトータルリターンは設定来期間(約4年)で年率換算およそ8~10%台を記録しており、高配当ETFの中では優秀な部類です(直近3年ではVYMと並び10%台)。これはカバードコール戦略により下落局面での下値抵抗力が高かったことと、インカムを再投資することで複利効果が得られるため。ただし、市場急騰局面ではコール売りの損失が発生するためリターンが抑えられる点には留意が必要となる。
まとめると以下のようになる。
- JEPIは分配金頼みで、株価はほぼ横ばい。短期インカム向き。
- VYMは株価+配当でトータルが強い、長期安定運用に最適。
- HDVは安定性を重視しつつ中堅の成績。
- SPYDは高配当好き向けだが、成長力は物足りない。
4. 税引き後の利回り(日本居住者の場合)
日本在住者が米国ETFから配当を受け取る場合、米国で10%の源泉徴収が行われ、その差引後金額に対して日本国内で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)課税されます。そのため二重課税後の手取り利回りは表面利回りのおよそ72%程度に減少します(=0.9×0.79685倍の約0.717倍)。各ETFの税引後利回りの目安は以下の通り:
- JEPI:約5.6%(手取り) – 税引前7.8%×0.717 ≈ 5.6%
- VYM:約2.1%(手取り) – 税引前2.95%×0.717 ≈ 2.1%
- HDV:約2.5%(手取り) – 税引前3.54%×0.717 ≈ 2.5%
- SPYD:約3.3%(手取り) – 税引前4.54%×0.717 ≈ 3.3%
上記は外国税額控除を利用しない場合の実効利回りです。外国税額控除制度を活用すれば米国源泉10%分を日本で取り戻すことが可能となり、結果として国内課税分20.315%のみが負担となります(実効手取り約79.7%、例えばVYMなら約2.4%手取り)。いずれにせよ、日本株の配当と比べ米国課税分だけ手取り利回りが低下する点は考慮が必要。
5. 日本から投資する際の注意点
① 二重課税と外国税額控除: 上述のように米国株式/ETFの配当には日米双方で課税される。確定申告で「外国税額控除」を申請することで、米国で源泉徴収された10%分を上限として日本の税額から差し引けます。これにより二重課税を緩和し、手取り利回りを向上させることが可能となる。外国税額控除をしない場合、配当金に約28%もの税がかかったままになるため、可能であれば控除を活用することが望ましい。なお、NISA口座の場合は日本課税分が非課税になる代わりに外国税額控除の適用が原則できず(米国源泉10%は戻らない)点に留意が必要。
② 為替リスク: 米国ETFへの投資では為替相場の変動リスクは避けられない。ドル建て資産のため、円高になると資産評価額や受取配当の円換算額が目減りし、円安になればその逆で有利になる。為替の影響は投資元本だけでなく配当金にも及ぶため、長期では円安恩恵・円高リスクの両面を考慮する必要がある。為替変動による評価損益は20万円を超えると確定申告が必要になる場合もありますので、頻繁な為替取引(円転・ドル転)には注意が必要。
③ 証券会社・取引市場: 米国ETFは日本の証券会社を通じて海外市場(主にNYSEやNASDAQ)で購入する形になります。主要ネット証券(SBI・楽天・マネックスなど)は米国ETFの取扱いがあるが、口座開設時に外国株取引の設定が必要。購入時には円を米ドルに為替交換してから取引する(一部証券会社では自動為替機能あり)。為替手数料や売買手数料は証券会社ごとに異なるため、コスト面も比較検討をしたほうがいい。なお、高配当ETFの中には東証上場のもの(例えばHDV等を円建てで投資できる投資信託やETFラップ商品)も存在するが、流動性や信託報酬の面で本家米国ETFに劣るケースがある。基本的には現地米国市場で本家ETFを買うのが低コスト。
④ 取引・税務の事務面: 米国ETFの分配金は通常年4回(JEPIは月次)ドル建てで支払われる。証券会社によっては受取りドルを自動で円転する設定も可能。特定口座で運用すれば日本国内税金の計算・徴収は証券会社任せにできるが、外国税額控除を受ける場合は別途確定申告が必要。また、配当金をドルのままプールし再投資に回す場合、為替差益が発生することもあるため申告要否に注意してほしい。これら事務手続きを踏まえても米国ETFは魅力的な商品だが、為替手数料の低い証券会社を選ぶ、特定口座(源泉あり)やNISA口座を活用するなど、手間とコストを抑える工夫をすると良い。
最後に、今回比較したJEPIと従来型高配当ETF(VYM/HDV/SPYD)は、それぞれリスク・リターン特性が異なる点にも注意が必要。JEPIはオプションプレミアムによる高収入で安定した現金収入を得られる反面、上昇相場で取り残されるリスクがある。一方、VYMやHDV、SPYDは株価の成長力と利回りのトレードオフ関係があり、特にVYMは利回り控えめながら増配と株価成長による総合力が高く、SPYDは利回り最重視ながら株価成長力が低いという特徴が見られる。投資目的(インカムゲイン重視か、トータルリターン重視か)に応じて、これらETFを適切に使い分けることが重要となる。
比較データまとめ
| 指標/ETF | JEPI (米国株プレミアム・インカム) | VYM (バンガード高配当株) | HDV (iシェアーズ高配当株) | SPYD (S&P500高配当株) |
|---|---|---|---|---|
| 運用開始 | 2020年5月 | 2006年11月 | 2011年3月 | 2015年10月 |
| 経費率 | 0.35% | 0.06% | 0.08% | 0.07% |
| 最新配当利回り(税引前) | 約7.5% | 約3.0% | 約3.5% | 約4.5% |
| 平均配当利回り(過去数年) | 約8%(※変動あり) | 約3.2% | 約3.7% | 約4.6% |
| 価格リターン(年率) | ~0%(設定来) | ~5–6%(10年) | ~4%(10年) | ~3–4%(8年) |
| トータルリターン(年率) | ~9–10%(設定来) | ~8–9%(10年) | ~6–8%(推定) | ~5–7%(推定) |
| 税引後利回り(手取り) | 約5.6% | 約2.1% | 約2.5% | 約3.3% |
注記: 税引後利回りは外国税額控除未考慮の場合の概算値(米国源泉10%+国内20.315%課税後)。外国税額控除適用時は各値のおよそ1.11倍(国内課税分のみ)となります。価格リターン・トータルリターンの年率は長期実績に基づく概算で、JEPIは設定来、SPYDは約8年、他は10年程度の期間で算出。


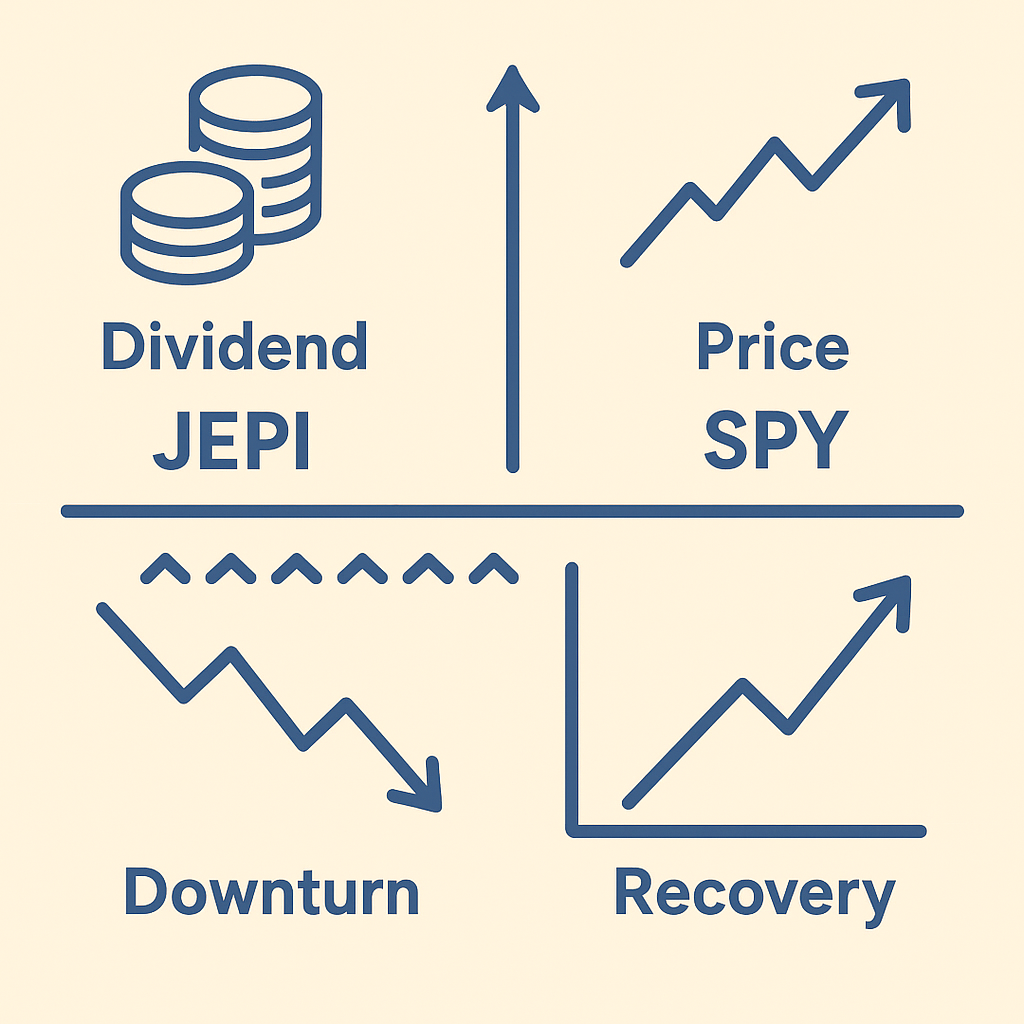
コメント