例題 [2022年1月] 少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
- 少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、 1,500万円が上限となる。
- 少額短期保険業者と締結する保険契約は、 生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
- 保険契約者(=保険料負担者) および被保険者を被相続人、 保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、 相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
各選択肢の検討
選択肢1
少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
🔴 誤り。
- 少額短期保険業者は、保険業法の特例的な規定(第3章の2)に基づいて登録され、監督を受ける存在です。
- 「保険業法の適用対象とならない」というのは明確な誤り。
選択肢2
少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。
🔴 誤り。
- 正しくは、生命保険タイプの契約について、
「同一の被保険者について合計1,000万円が上限」(※死亡保障の場合)です。 - 1,500万円という金額は根拠がありません。
選択肢3
少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
🔴 誤り。
- 少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の会員ではなく、保護の対象外です。
- したがって、破綻しても保険金の立替払いや補償は行われません。
選択肢4
保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
✅ 正解(適切)
- 少額短期保険であっても、「死亡保険金」として受け取った金額であれば、
相続税法第12条に基づく「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。 - 保険金が相続税法上の「みなし相続財産」に該当するためです。
✅【正解】
4. 保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
✅ 少額短期保険業者とは?
🔹 定義:
少額で短期間の保険契約を専門に取り扱う保険業者です。
一般の大手保険会社と比べて、小規模・簡易な保険を提供することを目的に、2006年の保険業法改正で新しく創設されました。
✅ 主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 監督法 | 保険業法の特例(第3章の2)により登録制(認可不要) |
| 取り扱える保険 | 生命保険・損害保険・医療保険など、少額・短期のもの |
| 保険金の上限 | 生命保険:被保険者1人につき合計1,000万円まで(死亡保障)損害保険:1事故あたり1,000万円まで |
| 契約期間の上限 | 1年以内(更新は可能) |
| 保護機構 | 保険契約者保護機構には加入していない(破綻しても補償されない) |
| 主な商品 | ペット保険、家財保険、葬祭保険、入院保険、感染症保険など |
✅ メリット・デメリット
▶ メリット:
- 審査が緩やかで加入しやすい
- 保険料が安く設定されている
- ニッチな保険(例:ペット保険、家財保険)を扱っている
▶ デメリット:
- 保険金額・保障期間が制限されている
- 保険契約者保護機構の対象外(破綻リスクあり)
- 資本力が小さく、経営の安定性にばらつきがある
✅ 登録数と実例(参考):
- 日本では現在、100社以上の少額短期保険業者が金融庁に登録されています。
- 例:ペットメディカルサポート、SBIプリズム少額短期保険、ジャパン少額短期保険 など
✅ どんな人に向いてる?
- 必要な保障だけをピンポイントで確保したい人
- 持病などで通常の保険に入れない人
- ペット保険などニッチな商品を探している人

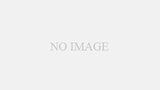
コメント