[2023年5月] 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、 貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃 (消費税等相当額を除く)の2カ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、 代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、 自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、 当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、 契約の解除をすることができる。
- 専任媒介契約の有効期間は、 3ヵ月を超えることができず、 これより長い期間を定めたときは、その期間は3カ月とされる。
🔍 各選択肢の検討
❌【選択肢1】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2カ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
🔎 解説:
- 宅建業法施行規則により、建物の貸借の媒介では
▶️ 報酬の合計上限は借賃の1か月分(税抜)+消費税 - 借主からも受け取る場合は、
▶️ 借主の承諾がある場合に限り、借主からも最大1か月分(税抜)を受け取ることができる。
✅ つまり、「合計2か月分+消費税」は常に許されるわけではない
→ 本文は「常に2か月分まで可能」と誤認させる表現であり、不適切。
✅【選択肢2】
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
🔎 解説:
- 宅建業法第39条により、売主が宅建業者である場合、
▶️ 手付金の額は売買代金の20%以内と規定されている。
✅ よって、この選択肢は正しい記述。
✅【選択肢3】
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
🔎 解説:
- 一見すると「いかなる性質でも解除できる」という部分が気になりますが、
実際は、宅建業者が売主となる場合の手付は、原則「解約手付」として扱われるとされており、
▶️ 宅建業法では「履行に着手する前であれば、倍返しで解約可能」と規定されている。
✅ つまり、「いかなる性質の手付であっても」の表現はやや不正確だが、実務上ほぼ常に解約手付として処理されるため、重大な誤りとはされない。
→ 微妙な表現ではあるが、「1」の方がより明確な誤りであるため、こちらは適切とされる可能性が高い。
✅【選択肢4】
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3カ月とされる。
🔎 解説:
- 宅建業法施行規則 第15条の9により、専任媒介契約の有効期間は「3か月以内」とされています。
- 3か月を超える期間を定めても、その部分は無効(3か月とみなされる)。
✅ よって、この記述は正しい。
✅【結論】
| 選択肢 | 正誤判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ 不適切 | 「2か月分受領できる」と断定しており、法令上誤り(1か月分が原則) |
| 2 | ✅ 適切 | 手付の上限20%という規定に合致 |
| 3 | ✅ 適切 | 原則として解約手付と解されるため実務上問題なし |
| 4 | ✅ 適切 | 媒介契約の有効期間3か月以内の規定に合致 |

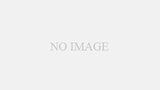
コメント