[2021年1月] 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、 本間においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、 それ以外の 建物賃貸借契約を普通借家契約という。 また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、 その存続期間は1年とみなされる。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、 その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、 存続期間を6カ月未満とすることはできない。
- 定期借家契約は、 公正証書によって締結しなければならない。
✅ 選択肢2(正解)
普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
🔍【解説】
- 借地借家法第31条では、
- 建物賃借人は、その建物を引き渡しされていれば、
- 賃借権を第三者(物権取得者)に対抗できると規定しています。
- 通常、民法では登記がなければ賃借権は第三者に対抗できないが、建物の賃借権については例外として「引渡しがあればOK」となる特則があります。
✅ よって、これは正しい記述(最も適切)です。
❌ 選択肢1
普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
🔍【解説】
- 借地借家法第29条によれば、
- 1年未満の期間を定めた普通借家契約は、期間の定めのない契約とみなされる。
- 「1年とみなされる」は誤り。
- 正しくは「期間の定めのない契約」とされます。
❌ 不適切
❌ 選択肢3
定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6カ月未満とすることはできない。
🔍【解説】
- 定期借家契約の期間に下限はありません。
- つまり、6カ月未満でも設定可能です。
- ただし、居住用で期間が1年未満の場合は、更新拒絶の通知義務が不要になるなどの規定はあります(借地借家法第38条第4項)が、契約自体は可能です。
❌ 不適切
❌ 選択肢4
定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
🔍【解説】
- 借地借家法第38条では、
- 定期借家契約は「書面(紙または電磁的記録)による契約」であることが必要で、
- 公正証書である必要はありません。
- 公正証書が必要なのは、定期借地権の一部(例:一般定期借地権、事業用定期借地権)です。
❌ 不適切
✅ 結論
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ | 「1年とみなされる」は誤り。正しくは「期間の定めのない契約」。 |
| 2 | ✅ 正解 | 引渡しがあれば登記がなくても第三者に賃借権を対抗できる(借地借家法31条)。 |
| 3 | ❌ | 定期借家契約には下限なし。6カ月未満でも契約可能。 |
| 4 | ❌ | 書面(紙または電磁的記録)で十分。公正証書は不要。 |
正解:選択肢2 ✅

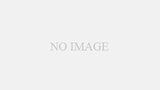
コメント