[2023年9月]相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者 (=保険料負担者) および被保険者が夫、 死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、 夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、 遺産分割の対象とならない。
- 契約者(=保険料負担者) および被保険者が父、 死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、 子が相続の放棄をした場合は、 当該死亡保険金について、 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、 相続税の課税対象となる。
- 被相続人の死亡により、 当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、 相続人がその支給を受けた場合、 当該退職手当金は、 相続税の課税対象となる。
選択肢の検討
【選択肢1】
契約者 (=保険料負担者) および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。
✅ 適切
- 死亡保険金は、受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象外です。
- よって、この記述は正しい。
【選択肢2】
契約者 (=保険料負担者) および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
✅ 適切
🔹 解説:
- 生命保険金は 「みなし相続財産」(相続税法第3条)であり、相続財産そのものではない。
- 相続の放棄をしても保険金の受取人であれば受け取ることができる。
- しかし、ここでのポイントは**非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)**の「適用の可否」です。
非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした者も含める(相続税法基本通達12-5)。
しかし!
- 放棄をした本人が生命保険金を受け取った場合、その人自身には非課税枠が適用されないのが原則です。
つまり、
| 状況 | 非課税枠の扱い |
|---|---|
| 相続放棄した人が受取人 | 非課税枠の適用を受けられない |
| 相続放棄していない人が受取人 | 適用を受けられる |
✅ よってこの選択肢は 「子が相続放棄をした場合は、非課税の適用を受けられない」と書かれており、正しい 内容です。
【選択肢3】
老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
❌ 不適切(これが正解)
- 老齢年金の未支給年金は、年金法により相続ではなく、遺族の固有の権利として支払われる。
- つまり、相続税の対象ではなく、「所得税(一時所得)」の対象です。
- この選択肢は明確に誤り。
【選択肢4】
被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。
✅ 適切
- 死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合、相続税の課税対象になります(相続税法施行令第3条1項3号)。
- この記述は正しい。
✅ 最終結論
| 選択肢 | 結論 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適切 | 死亡保険金は遺産分割の対象外 |
| 2 | ✅ 適切 | 相続放棄した人は非課税枠の適用を受けられない |
| 3 | ❌ 不適切 | 未支給年金は相続税ではなく所得税の対象 |
| 4 | 適切 | 死亡退職金は相続税の対象(3年以内) |

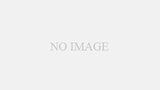
コメント