[2023年5月] 不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産所得の金額の計算上、本年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
- 不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
- 不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、 契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
- アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、 特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
✅ 各選択肢の検討
❌ 1. 不適切(正解)
不動産所得の金額の計算上、本年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
→ 誤りです。
建物の減価償却については、平成10年4月1日以降に取得した建物については「定額法」が強制適用となっています。
つまり、定率法は選択できません。
▶ よって、この選択肢が「最も不適切」。
✅ 2. 正しい
不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
→ 正しいです。
税法上、所得税・住民税は個人の税金であり、必要経費に算入できません。
(ただし、事業税は必要経費にできます)
✅ 3. 正しい
不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
→ 正しいです。
これは「発生主義」による収入認識の原則です。
現金の受領日ではなく、契約上の支払期日が収入計上のタイミングになります。
✅ 4. 正しい
アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
→ 正しいです。
これは、いわゆる「5棟10室基準」の一部。
「おおむね10室以上」は、事業的規模と判断される基準の一つです。
✅ 結論(正解)
| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ 不適切 | 建物の償却は定額法が強制適用。定率法は選択できない。 |
| 2 | ✅ 適切 | 所得税・住民税は必要経費にならない。 |
| 3 | ✅ 適切 | 賃料の支払日=収入計上日とする発生主義が原則。 |
| 4 | ✅ 適切 | おおむね10室以上なら事業的規模と推定される。 |

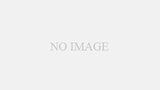
コメント