[2023年1月]相続税の計算に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。 なお、 本間において、 相続の放棄をした者はいないものとする。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、 法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、 実子がいる場合、 2人に制限される。
- 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は 相続税額の2割加算の対象者となる。
- 法定相続人が被相続人の配偶者のみである場合、 「配偶者に対する相続税「額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。
各選択肢の検討
選択肢 1:
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。
✅ 適切
🔹 解説:
- 相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 - 法定相続人に含めることができる養子の数には制限があります:
| 実子の有無 | 含められる養子の上限 |
|---|---|
| 実子あり | 1人まで |
| 実子なし | 2人まで |
- しかし、本選択肢では「実子がいる場合、2人に制限される」と述べており、これは 誤り。
❌ よって、この選択肢は 不適切。
選択肢 2:
相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
❌ 不適切
🔹 解説:
- 相続税額の2割加算(相続税法第18条)は、被相続人の配偶者・子・父母などの直系血族や養子以外の者に適用されます。
- 代襲相続により孫が相続人となった場合は「被相続人の子とみなされる」ため、2割加算の対象外です。
❌ よって、この記述は 誤り。
選択肢 3:
法定相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。
✅ 適切
🔹 解説:
- 配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2)では、配偶者が取得した遺産のうち、
① 法定相続分相当額 または
② 1億6,000万円までの金額
のいずれか多い金額まで非課税となります。 - 本問の条件では、相続人が配偶者1人のみなので、全遺産を相続しても非課税になることが多く、結果的に相続税が発生しないケースが非常に多いです。
✅ よって、この選択肢は 適切。
選択肢 4:
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。
❌ 不適切
🔹 解説:
- 相続税法における「配偶者」とは、**民法上の正式な婚姻関係にある者(=婚姻届を提出した者)**を意味します。
- 内縁関係の配偶者は対象外です。
❌ よって、この記述は 誤り。
✅ 結論(最も適切なもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ | 養子は実子がいる場合、1人までしか含められない |
| 2 | ❌ | 代襲相続の孫は「子とみなされる」ため2割加算されない |
| 3 | ✅ 正しい | 配偶者だけが相続人なら、実質的に相続税は発生しない |
| 4 | ❌ | 内縁の配偶者は「配偶者の軽減」対象外 |

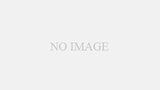
コメント