[2022年9月] 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、 本間においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、 それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、 その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、 正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、 事業の用に供する建物については締結することができない。
- 定期借家契約において、 その賃料が、 近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
🔍 問題の前提
- 定期借家契約(第38条):期間満了で終了。更新なし。書面契約が必須。
- 普通借家契約(第26〜28条):更新あり。正当事由が必要。
各選択肢の検討
✅ 選択肢1
普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
🔍【解説】
借地借家法第29条により、1年未満の期間を定めた普通借家契約は「期間の定めのない契約」とみなされ、1年とはみなされない。
📌【誤りの理由】:
「1年とみなされる」は誤りで、「期間の定めのない契約」とみなされます。
❌ 不適切
❌ 選択肢2
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
🔍【解説】
→ 借地借家法において、「正当事由が必要なのは賃貸人」側だけです。
- 賃借人は、正当事由がなくても契約更新を拒否・終了可能です(民法に従う)。
- 一方、賃貸人は更新拒否や解約には正当事由が必要(借地借家法 第28条)。
❌ 不適切
❌ 選択肢3
定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
🔍【解説】
→ 誤りです。
- 定期借家契約(借地借家法第38条)は、居住用でも事業用でも締結可能です。
- 事業用建物であっても、書面(書類 or 電磁的記録)で契約すれば定期借家契約にできます。
❌ 不適切
✅ 選択肢4
定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
🔍【解説】
→ 正しい記述です。
- 借地借家法第38条第5項により、定期借家契約においては、賃料増減額請求権を排除する特約が有効とされています。
- 普通借家契約では無効ですが、定期借家契約に限っては有効です。
✅ 適切な記述
✅ 結論
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ | 「1年とみなされる」は誤り。「期間の定めのない契約」とされる。 |
| 2 | ❌ | 正当事由が必要なのは賃貸人側。賃借人には不要。 |
| 3 | ❌ | 定期借家契約は居住用にも事業用にも使える。 |
| 4 | ✅ 正解 | 定期借家契約では賃料増減を排除する特約は有効。 |
正解:選択肢4 ✅

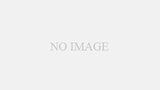
コメント