[2022年9月] 団体生命保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 団体定期保険 (Bグループ保険) は、 従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、 毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
- 総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、 当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。
- 住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、 被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、 死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。
- 勤労者財産形成貯蓄積立保険 (一般財形) には、 払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。
各選択肢の検討
選択肢1
団体定期保険 (Bグループ保険) は、 従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、 毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
✅ 正しい(適切)
- Bグループ保険(任意加入型の団体定期保険)は、企業が団体契約し、従業員が任意で加入できる1年更新の定期保険。
- 保険金額は、本人が所定の範囲で自由に選択・見直し可能。
- 福利厚生や遺族保障の補完として使われる。
選択肢2
総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。
❌ 誤り
- ヒューマン・ヴァリュー特約の保険金受取人は企業(団体)であり、遺族ではありません。
- 目的は、企業の損失補填であって、遺族補償ではない。
選択肢3
住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、 被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、 死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。
❌ 誤り
- 団信(団体信用生命保険)の保険金受取人は金融機関(債権者)であり、遺族ではない。
- 債務者(ローン利用者)が死亡すると、保険金によりローン残高が完済される仕組み。
選択肢4
勤労者財産形成貯蓄積立保険 (一般財形) には、 払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。
❌ 誤り
- 税制優遇のあるのは、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄であり、一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)には非課税措置はない。
- 利子非課税の限度額(年金+住宅の合計)550万円(うち年金は385万円まで)が適用されるのは税制適格型のみ。
✅ 正解:1
団体定期保険 (Bグループ保険) は、 従業員が任意加入でき、毎年保険金額の見直しも可能な1年更新型の保険。
財形貯蓄
現在でも 「財形年金貯蓄」 と 「財形住宅貯蓄」 の2つは、条件を満たすことで利子等の非課税措置が適用されます。
✅ 現行制度の概要(2024年時点)
| 区分 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 |
|---|---|---|
| 目的 | 老後の年金資金の準備 | 住宅の取得・改修の資金準備 |
| 対象者 | 55歳未満の勤労者 | 55歳未満の勤労者 |
| 積立期間 | 最短5年以上 | 最短5年以上 |
| 非課税限度額 | 元利合計 385万円まで | 元利合計 550万円まで(年金との合算) |
| 非課税対象 | 預貯金、保険、信託の利子等 | 同左 |
| 利用条件 | 年金形式で5年以上受取 | 自己名義の住宅取得・改修に充当 |
| 税制優遇 | 利子が非課税(本来20.315%) |
🔍 注意点
- 年金財形と住宅財形の合計で550万円までが非課税枠
- 目的外に使った場合(年金受給前の中途解約など)は、非課税が取り消され課税対象になります
- 一般財形には非課税措置は一切ありません
ご希望であれば、各制度の具体的な利用事例や、iDeCo・NISAとの比較もご説明可能です。

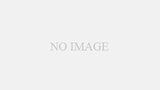
コメント