[2020年1月]所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所得税は、納税者が申告をした後に、 税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、 非居住者、 内国法人、 外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
- 所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、 それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 課税総所得金額に対する所得税額は、 課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。
✅正解:2
各選択肢の解説
❌1. 誤り
所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税は 申告納税方式(=納税者が自分で所得や税額を計算して申告・納付)を採用しています。
- 賦課課税方式(=税務署が課税額を決定)は、固定資産税などに見られます。
▶ 誤り
✅2. 正しい
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
- 一見、法人は所得税の対象ではないように思われますが、所得税法上では、外国法人が日本で得た所得に対して源泉徴収されるケースがあるため、実務上・制度上、この4分類で納税義務が整理されていることは適切な表現とされます。
- FP試験では「制度理解」として、これが正答になります。
▶ 正解
❌3. 誤り
所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して…
- 所得税法における所得の種類は10種類です:
- 利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得。
- 「14種類」という表現は誤りです。
▶ 誤り
❌4. 誤り
所得税は、一律20%の税率により計算する。
- 所得税は、**超過累進税率(5%〜45%)**です。
- 一律20%ではなく、課税所得が増えるほど税率が上がる方式です。
▶ 誤り
🔻まとめ表
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ | 所得税は申告納税方式。賦課課税方式ではない。 |
| 2 | ✅ | 所得税法では4区分の納税義務が制度上存在。FP試験ではこれが正解。 |
| 3 | ❌ | 所得は10種類。14種類という記述は誤り。 |
| 4 | ❌ | 所得税は超過累進税率(5〜45%)。一律20%は誤り。 |
🔷 内国法人(ないこくほうじん)
定義:
日本の法律に基づいて設立された法人
✅ 具体例:
- 日本国内で設立された株式会社・合同会社・医療法人・学校法人など
- 日本法人のトヨタ自動車株式会社、三菱UFJ銀行 など
✅ 特徴:
- 法人税の対象(日本で得た所得も海外で得た所得も課税対象)
🔷 外国法人(がいこくほうじん)
定義:
外国の法律に基づいて設立された法人
✅ 具体例:
- アメリカのApple Inc.
- 韓国のSamsung Electronics
- イギリスのHSBC
✅ 特徴:
- 原則として日本での**源泉所得(国内源泉所得)**に対してのみ課税
- 例:日本の企業から得た利子、配当、使用料など
- 所得税や法人税の対象になるケースもある(日本で活動する場合)
🔻補足:所得税との関係
外国法人が日本で得た収入(たとえば、日本の企業から受け取るロイヤリティなど)は、日本で**源泉徴収(=所得税の形で天引き)**されることがあります。
そのため、所得税法の中でも「内国法人・外国法人」の区別がされるというのが、FP試験の出題の背景です。
🔚まとめ
| 項目 | 内国法人 | 外国法人 |
|---|---|---|
| 設立国 | 日本 | 日本以外の国 |
| 根拠法 | 日本の会社法など | 外国の法律 |
| 課税対象 | 全世界所得(日本+海外) | 原則として日本の所得のみ |
| 例 | トヨタ、三菱UFJ | Apple, Samsung |
法人に対する税金は「法人税」であって、「所得税」ではありません。
ただし、状況によっては**「法人にも所得税が課されるケース」がある**ため、FP試験などではその点が問われることがあります。以下で詳しく説明します。
🔷 所得税と法人税の違い
| 税金の種類 | 対象 | 具体例 |
|---|---|---|
| 所得税 | 個人(自然人) | サラリーマン、自営業者、投資家など |
| 法人税 | 法人(会社などの団体) | 株式会社、合同会社、NPO法人など |
🔸じゃあ、「法人に対する所得税」って何?
法人自体が本来対象となるのは「法人税」ですが、外国法人などの一部のケースでは、「源泉所得」に対して所得税が課されることがあります。
✅ 例:外国法人が日本で収入を得る場合
たとえば…
- アメリカの会社(外国法人)が日本の企業からロイヤリティや利子を受け取る
- → 日本の企業が、その支払金額から20.42%の所得税を源泉徴収する
- → この税金は**「所得税」として課税される**
このように、「法人」に対しても源泉所得税という形で所得税が課されることがあるのです。
🔸所得税法で法人が出てくる理由
だから、所得税法の条文や制度説明では、以下のように納税義務者が整理されます:
- 居住者(日本に住所や居所がある個人)
- 非居住者(海外に住んでいて、日本で所得がある個人)
- 内国法人(日本の法人)
- 外国法人(海外の法人)
この整理は、主に源泉徴収や課税対象の明確化のために行われます。
✅ 結論
- 法人の通常の税金は「法人税」であり、「所得税」とは別です。
- しかし外国法人などが日本で所得を得るときに、所得税が源泉徴収されることがあるため、制度上「法人に対する所得税」が存在する。
- そのため、FP試験などでは「所得税の納税義務者として、内国法人・外国法人も含まれる」という選択肢が正解になることがある。

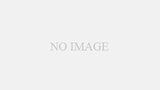
コメント