[2019年9月]生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、 保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険金額を減額することにより、 保険料の負担を軽減する方法がある。
- 保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、 保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、 契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
- 保険料の払込みを中止して、 その時点での解約返戻金相当額を基に、 元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
- 保険料の払込みを中止して、 その時点での解約返戻金相当額を基に、 元の契約よりも保険金額が少なくなる保険 (元の主契約と同じ保険または養老保険) に変更する払済保険があり、 特約はすべて継続される。
各選択肢の検討
選択肢1
保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
✅ 適切
- 保険料の負担を軽減したいときに、保険金額を減らすことで保険料を下げることは可能。
- 一般的な対処法のひとつ。
選択肢2
保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
✅ 適切
- 自動振替貸付(APL: Automatic Premium Loan)制度は、保険料の未納があっても、解約返戻金の範囲内で保険会社が立替え、契約を失効させない制度。
- 立て替え分には利息が付く。
選択肢3
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
✅ 適切
- 延長保険(延長定期保険)は、保険料の払込を中止したうえで、解約返戻金を原資に元の保険金額はそのまま、保障期間を短くした定期保険に自動転換する制度。
- 元の保障額を保ちながら、一時払いの形に変える。
選択肢4
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。
❌ 不適切 → 正解
- 払済保険とは、保険料の払込みを中止し、解約返戻金をもとに保険金額を縮小した終身保険などに変更する方法。
- ただし、❗️「特約」は基本的に消滅(継続されない)。
- この選択肢の「特約はすべて継続される」という部分が誤りです。
✅ 結論:最も不適切なのは 4
「払済保険に変更しても特約はすべて継続される」という記述は誤りです。
通常、**特約は終了(消滅)**します。
✅ 延長保険とは
延長保険とは、生命保険の保険料を支払えなくなったときの対応策のひとつです。
契約者が保険料の払込みを中止した際に、それまで積み立てた解約返戻金を使って、新たに一時払いの定期保険に自動的に切り替える方法です。
🔁 延長保険の仕組み(ポイント)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料 | 払込みは中止(もう支払わない) |
| 原資 | その時点の解約返戻金 |
| 保障内容 | 元の契約と同じ保険金額で、期間が短くなる |
| 保険期間 | 保険料相当の期間(例:数年)に延長される定期保険 |
| 保険種類 | 一時払いの定期保険に切り替わる |
🔹 具体例で解説:
たとえば…
- 元の契約:終身保険(保険金額1,000万円、保険料月1万円)
- 経過年数:10年(解約返戻金が100万円貯まっている)
- 払込みをやめる → 解約返戻金100万円を使って「延長保険」へ移行
この場合:
- 保険金額1,000万円はそのままキープ
- ただし、新たに設定された保険期間は「100万円分の一時払いで購入できる期間」(例:定期保険として5年間)
📌 特徴・メリット・デメリット
✅ メリット
- 保険金額はそのまま維持できる
- 保険料の払い込みを止めても、保障を一定期間継続できる
- 手続き不要で自動的に移行されることもある
❌ デメリット
- 保障期間が限られる(長期間保障はできない)
- 保険期間満了後は無保険になる
- 特約は通常失効する
🆚 払済保険との違い
| 項目 | 延長保険 | 払済保険 |
|---|---|---|
| 保険金額 | 元の契約と同額 | 減額される |
| 保険期間 | 短くなる(定期) | そのまま(終身など) |
| 特約 | 消滅 | 消滅 |
| 保険料 | 以後支払い不要 | 同左 |
✅ 向いているケース
- 今すぐの保障は必要だが、保険料がもう払えない
- 一定期間だけでも保障を残したい
- 解約は避けたいが終身継続も難しい

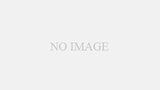
コメント