[2018年9月]相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。
- 相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ) となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 相続税を金銭で納付するために、 相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、 相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
- 相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、 それが困難な場合には、納税義務者は、 任意に延納または物納を選択することができる。
各選択肢の検討
選択肢 1:
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ) となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
❌ 不適切
🔹 解説:
- 配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2)を適用するためには、相続税の申告書の提出が必要です。
- たとえ納税額がゼロであっても、**軽減の適用を受けるには「申告が要件」**です。
👉 よってこの選択肢は 誤り。
選択肢 2:
相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
❌ 不適切
🔹 解説:
- 土地を売却して得た収入は、譲渡所得として所得税の課税対象です。
- 相続税の納付目的で売却したとしても、譲渡所得の課税は免除されません。
👉 よってこの記述も 誤り。
選択肢 3:
期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
✅ 適切
🔹 解説:
- 相続税の申告と納付の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です(相続税法第27条)。
- 一般的には、被相続人の死亡日=相続の開始を知った日となるため、死亡翌日から起算して10ヶ月です。
👉 よって、この記述は 正しい。
選択肢 4:
相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
❌ 不適切
🔹 解説:
- 延納・物納を希望する場合は、税務署長の許可が必要です(相続税法第34条・第35条)。
- 「任意に選択できる」わけではなく、一定の要件と申請が必要です。
👉 よってこの記述は 誤り。
✅ 最終結論
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ❌ | 軽減を受けるには申告が必要 |
| 2 | ❌ | 土地譲渡益には所得税が課される |
| 3 | ✅ 最も適切 | 申告・納付期限は「死亡を知った日」の翌日から10ヶ月以内 |
| 4 | ❌ | 延納・物納は任意ではなく、許可制 |

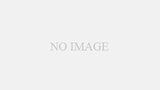
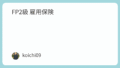
コメント